戦国大名の経済学 川戸 貴史 著
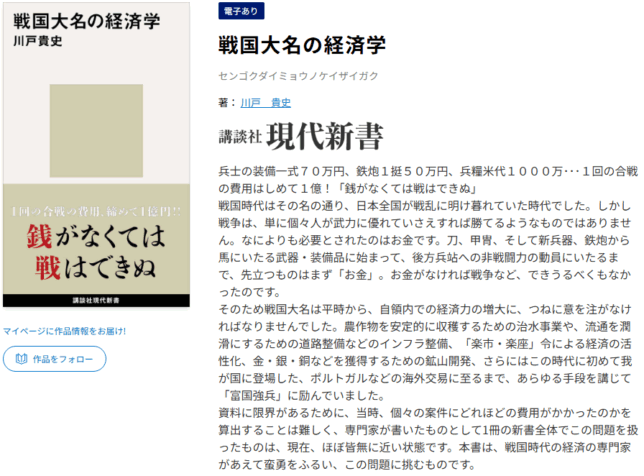
歴史好きなもので、背表紙を見た瞬間、とりあえずこれは読むしかなかろうと思った本です。
内容的には、しばしばありがちな当時の取引や物の価値を現在価値に置き換えてみたりすることで、当時の経済活動や経済規模、軍事活動などのインパクトを現代人の肌で感じられるようにしてくれている本です。戦国大名といえば、戦場の勝ち負けで全て動いてきたかのように思ってしまいますが、多様な経済活動をしており、税収UP、経済の活性化、生産力のUPや技術導入など、国力UPのために本当にいろんなことをしていたんだというのがわかります。
ただ、ここまでなら他の本でもしばしば見られる内容かと。この本で一番興味深かったのは第6章以降。
- 日本国内の銭不足と、新たな国際通貨としての銀貨の浸透
- 銭不足による貫高制の崩壊と石高制への移行
- 金貨、銀貨の国内蓄積による「金、銀、米」の三貨制の成立
貫高という言葉も石高という言葉も以前から聞き知ってはいました。江戸時代に、米価が大変重要であったことも、金銀の貨幣経済が浸透していったことも知ってはいました。が、これらの間の橋渡しが戦国時代後半に、南蛮商人とも絡みながら進んでいったことを、こんなにわかりやすく示してくれた本はこれが初めてです。なるほど、と思わず膝を打ちました。
中国からの輸入銭を基軸に成立していた日本の貨幣経済は、戦国期に、多くの税収が銭で徴収されるようになるほど、一旦は浸透していたわけです。ところが、中国側の銭生産の下落や輸出抑制によって日本は急速に貨幣不足に陥ります。同時期に、南蛮商人の来航と国内の銀山開発が進み、日本は徐々に大航海時代の銀貨経済圏に組み込まれ、最初は輸出品として利用された銀が国内でも貨幣として流通するようになります。(同時に、中国に大量に流れた日本銀によって中国の貨幣不足は、銀貨という高額貨幣の追加により解消していくわけですね。)さらに金山開発が進むと、金貨という更に上位の高額貨幣が登場することにより、経済発展の素地が生まれていくわけです。
「信長の野望」でちらほら出てくる「撰銭令」や「差出検地」ってこういうことだったのね!と今更ながら気付かされました。やっぱり信長の野望を作ってる人、すごいですね。
銭不足になる中で、悪貨が良貨を駆逐していく様も見事な描写でした。トーマス・グレシャムの法則「悪貨は良貨を駆逐する」は本当なのですね!確かに、皆が質の良いと思う貨幣は、皆が抱え込んでしまうため市場から消えてしまいます。結果、悪貨ばかりが市場に残り、市場は更にインフレ(貨幣価値の下落)が起こっていくことになります。戦国末期は銭不足からこれがどんどん進行していく状況だったのでした。
戦国時代の経済学として、良著だと思います。大変読みやすい文体でサクッと読んでしまいました。