海洋帝国興隆史 ヨーロッパ・海・近代世界システム 玉木 俊明 著
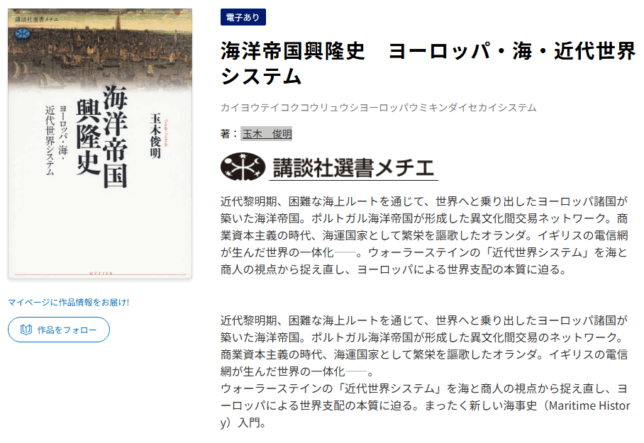
ポルトガルから始まり、スペイン、オランダ、イギリスと進む海洋帝国の興亡と、その要因を探った本です。歴史では、陸より海のほうが好きな私としては、ついつい手を出してしまいました。
北海やバルト海交易が専門の著者ですので、どうしてもそちらに寄った記述にはなってしまっていましたが、比較的バランスよく世界中に目を向けて書いてくれていると思います。
海洋帝国といえば、ついつい海軍のほうに目をむけてしまいがちですが、なんの富も産まない軍艦が突然生まれてくるわけもなく、それを支える巨大な商船隊や交易網があるわけです。ヨーロッパの国々の海洋進出は、植民地拡大と足並みをある程度揃えて進んだために、海外領土こそが富の源泉とも思われがちなところ、実は一番儲かったのは植民地経営や収奪ではなく、商品(ときには奴隷だったりもしましたが)を運ぶ「物流業」こそが一番儲かったのでは、というのが一番興味深かった指摘でした。
確かに、ポルトガルもオランダもさして植民地を持ったわけではありませんが、強力な海洋帝国として存在したわけで、それを説明するにはちょうど良い理解ですね。オランダによる物流網の支配に対抗するために、イギリスがイギリスの貿易はイギリス船を使えと航海法を打ち出し英蘭戦争になったんだ…との指摘、なるほどと思いました。
今でこそ、物流の位置づけは随分低くなりましたが、コロナ禍以降、徐々に陸運も海運も見直しの機運が高まっているようにも感じます。アメリカが急に造船業と騒ぎ出したのも、何やら絡みそうな話ではありますね。書きぶりも重たくなく、海洋史好きには面白く読みやすい本でした。